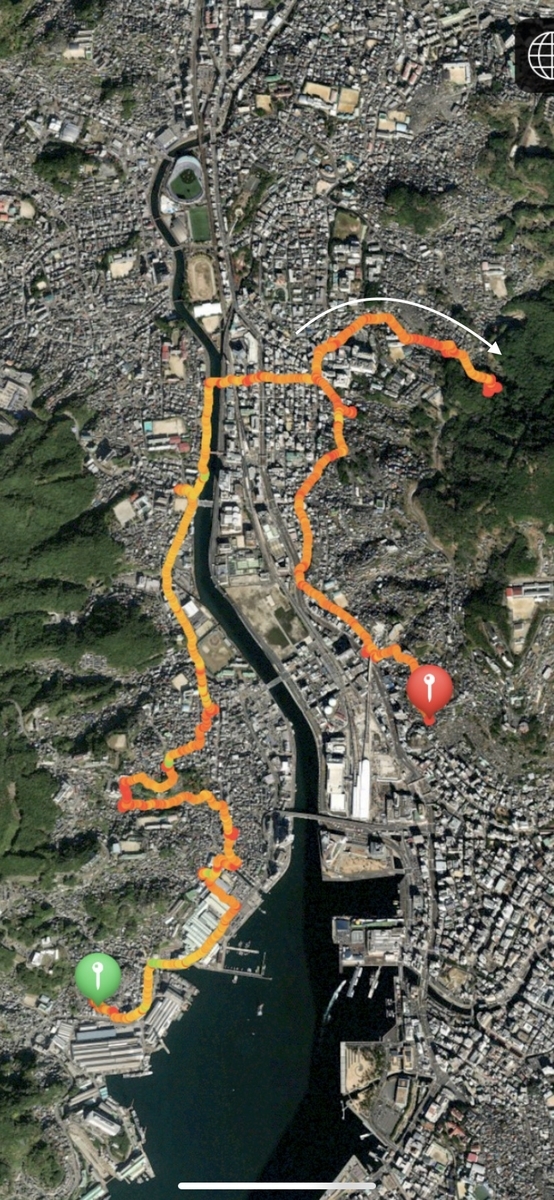
長崎四国八十八ヶ所霊場巡りも6回目を迎え、いよいよ満願の日となった。集合場所で先達から説明を受ける。「いよいよ今日は満願成就の日を迎えました。今日の参拝は感謝の気持ちで行ってください。今日の参拝では、全員無事に八十八ヶ所巡りができたことに、お守りいただいたことに感謝の合掌をしてください。合掌は心を込めておこなってください。合掌の形がみなさんバラバラですね。皆さん手を合わせて合掌してみてください。まず真っ直ぐ立ってください。みぞおちの前で手を合わせてください。角度を45度にしてください。おやゆびを立てないで5本の指を揃えてください。自然なきれいな合掌を心がけてください」と合掌について指導を受けて出発する。


今日、最初の札所は第39番峯巌寺観音堂である。浄土宗峯巌寺の境内の一角に観音堂が建てられて、そこにご本尊の観世音菩薩がお祀りされている。読経して参拝する。


次の札所へ行く途中、建物の切れ目から港と対岸風景を見る。私は対岸に住んでいるので、こちら側から見る港と対岸風景はめったに見ない。その分新鮮に感じる。長崎だけど長崎ではないような感じがする。与謝野鉄幹は、「長崎の 円き港の青き水 ナポリを見たる 眼にも美し」と詠んでいる。いつまでも美しい港であって欲しいと思う。


続いて第86番鳥居大師堂へ行く。住宅街の一角に大師堂が建てられ、そこにご本尊の弘法大師が祀られている。読経して参拝する。そこから15分ほど歩くと第23番萬福寺へ着く。ここの本堂にご本尊の薬師如来が祀られている。読経して参拝する。


続いて第43番江の浦大師堂へ行く。急な坂道をどんどん上っていくと、弘法大師の大きな像が見えてくる。そこのお堂が江の浦大師堂である。鍵がかかっていて中の様子は見えない。外に立ち読経して参拝する。


続いて、第22番泰三寺へ行く。泰三寺は曹洞宗のお寺でご本尊は釈迦如来である。曹洞宗は高祖道元禅師が日本に教えを伝えたと聞いていたので道元禅師は中国の方と思っていたが、道元禅師は日本人で23歳の時に南宋に渡り、禅の教えを会得して日本で広めたようだ。読経して参拝する。


泰三寺を出て30分ほど町中を歩いていくと、第74番梁川町観音堂へ着く。梁川町観音堂のご本尊は観世音菩薩である。梁川町観音堂は今から77年前は町内の別の場所にお堂が建てられ祀られていたが、原子爆弾によってお堂が倒壊したため幾度か場所を移り、最終的に現在地にお堂が建てられお祀りされることになった。昔から町内の仏様として信仰されている観音堂である。読経して参拝する。


今日一番の難所である上り坂を上っていく。一気に上っていきたいところだが、きつくて途中休憩をしながら上っていく。そして第4番高野山穴弘法寺へ着く。ご本尊は愛染明王である。読経して参拝する。お参り後、茶菓のお接待を受ける。


穴弘法寺の境内にはさらに二つの札所が設けられている。一つは穴弘法寺から歩いて5分ほどのところにある第52番岡部大師堂である。ご本尊は十一面観音である。読経して参拝する。続いて第21番奥の院霊泉寺へ行く。ここのご本尊は大日如来である。読経して参拝する。



穴弘法寺から町の方へ下りていく。そして、次の札所第83番観音堂へ行く。83番観音堂は77年前の原爆によってお堂は焼けたが観世音菩薩像は欠損部を修復して現在もお祀りしている。観音堂に掲示されている被曝当時の観世音菩薩の写真を見ると、二度とあの惨禍を繰り返してはならないと強く思う。


続いて第37番御船蔵町地蔵堂へ行く。ご本尊は地蔵菩薩である。読経して参拝する。そして最後の第58番西坂町地蔵堂へ行く。ここの地蔵尊は1668年に海中より引き上げられ運搬途中、この地で休憩したところ、再び運び出そうとしたが重くて動かせず、またこの地で祀るようお告げがあり、この地で祀ることになったといういわれのある地蔵尊で、1796年(寛永8年)弘法大師と合わせてお祀りすることとなり現在に至っていると書かれてあった。海から引き上げられ350年以上の長きにわたって多くの人々の願いを聞きいれてきた地蔵尊を前に、読経して参拝する。
長崎四国八十八ヶ所巡りを結願した。多くの仏様に出会えた。仏様を前にしてただお顔を眺めるだけであった。仏様の御尊顔を拝するのみであった。いろんな表情の仏様に会えた。優しいお顔にも激しい怒りのお顔にも会えた。いろんなお顔に会えて多くの物語を聞けたのは楽しかった。また、また機会があれば祈りの旅をしてを昔の人の声に耳を傾けたいと思う。無事に満願成就できたことを諸々の仏様に感謝である。合掌